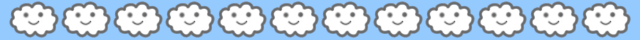
- 小
- 中
- 大
- テキストサイズ
【呪術廻戦】私と坊やと、晴れのち○○
第1章 私と坊やと、雨のち雨。
挨拶を終え、五条家へ戻る車の中。
坊やはさすがに疲れたのか、私の膝の上に頭を乗せて規則正しい寝息を立てている。
小さな背中に手を置いて一定のリズムで優しく叩く。
私の身体も疲労しきっていた。
車のドアに寄りかかり、息を吐く。
疲れた、本当に。
きっと坊やは今日一日で汚い世界を見たんじゃないかな。
言葉の意味はわからなくとも、大人の態度で私が受け入れられていないということはなんとなく理解したと思う。
大人の悪意がいかに卑屈で陰湿で狡猾なのか。
ああ、早く帰ってゆっくり寝たい。
あ、いっけね。
布団ないんだった。
明日、買いに行こうかどうしようか。
お金がないからな。
まぁ、いいや。
どうでもいい。
今は何も考えたくないなぁ。
寝ている坊やに目をやれば、親指をしゃぶっていて、思わず笑みがこぼれた。
まだ乳離れができないのか、君は。
そっとその指を離せば、口がもにゅもにゅと動いて、ああ、なんてかわいらしい子供なのだろうか。
寝ている時だけは。
私も静かに目を閉じた。
うん、この子のために命を落とすつもりは毛頭ないけど。
でもこの子が大きくなって自分で自分を護れるくらいまでは。
私は私の命をこの子のために使おう。
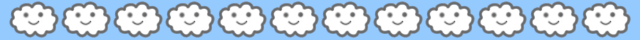
スマホ、携帯も対応しています
当サイトの夢小説は、お手元のスマートフォンや携帯電話でも読むことが可能です。
アドレスはそのまま
http://dream-novel.jp

 ピックアップする
ピックアップする