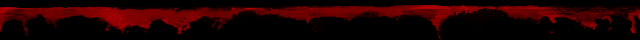
- 小
- 中
- 大
- テキストサイズ
歪み
第1章 懺悔
「だから言ってるじゃない、あの子は置いていきましょう」
「でも祟られたらどうする。あの子は不吉すぎる」
「海外までは追ってこないわよ」
「でも家はどうする。あの子を引き取っていいなんて言う親戚は…」
両親の会話を遮るように家を出る。
慌てていたため靴を履き忘れたが、裸足で石を踏んでも気にせずに走る。
「とーじ、とーじ」
たった一人の友達の名前を呼び暗い中を進む。
電灯が不気味に点灯を繰り返していた。
怖いからと止まれない。
「とーーじーー!」
7歳の子供は叫ぶことしかできない。
集まってくるのは黒い影ばかり。ソイツらは甚爾が言ってた呪霊だ。
は顔を下げてひたすら走っていると黒い何かにぶつかった。
「どうした?」
突撃したのは甚爾の長い足。黒いシャツに白いパーカーを着ていた。
いつの間にか周りにいた呪霊は消えている。安心しては足にしがみつくと大きな手が頭の上に乗った。
「おい、黙ってたら分かんねぇだろ」
ぐしゃぐしゃと乱暴に撫でられるが頭を撫でられたことがないはその行動すら憧れていたものだった。腰に腕が伸びて甚爾の太い腕の上に乗せられる。ぐずっと鼻をすすると空いている手が伸びてきて親指で涙を拭われた。
「パパとママが…」
両親の名前を言うと甚爾の眉が寄る。彼も家族という物にいい思い出などない。思い出すのは最悪な思い出ばかり…
自分たちと異質なものを排除する一族にはうんざりだ。
「…とーじと離れたくない」
友達と離れたくない一心で甚爾の胸にしがみつく。
一応仕事仲間はいるが、友達はいない甚爾はをえらく気に入っていた。今だって、に会いに毎日川へ寄っていし、近づく呪霊を切り刻んでいる。
「どういうことだ?」
「とおくへ行こうって話してた…でも行きたくない。わたし、とーじと一緒がいい」
そもそも両親と一緒に行けるかも分からないが…
「なら俺と来るか?」
は初めて誘われて驚いて小さな目を大きく見開く。
両親にもクラスメイトにもどこかへ行こうと言われたことは無かった。
「いいの?」
「俺たちは“お友達”なんだろ」
「うん!とーじのお友達!」
首を傾げた甚爾に大きく頷く。
友達とはやっぱり心強い。
「でもどうするの?」
「ガキは心配すんな」
「でも祟られたらどうする。あの子は不吉すぎる」
「海外までは追ってこないわよ」
「でも家はどうする。あの子を引き取っていいなんて言う親戚は…」
両親の会話を遮るように家を出る。
慌てていたため靴を履き忘れたが、裸足で石を踏んでも気にせずに走る。
「とーじ、とーじ」
たった一人の友達の名前を呼び暗い中を進む。
電灯が不気味に点灯を繰り返していた。
怖いからと止まれない。
「とーーじーー!」
7歳の子供は叫ぶことしかできない。
集まってくるのは黒い影ばかり。ソイツらは甚爾が言ってた呪霊だ。
は顔を下げてひたすら走っていると黒い何かにぶつかった。
「どうした?」
突撃したのは甚爾の長い足。黒いシャツに白いパーカーを着ていた。
いつの間にか周りにいた呪霊は消えている。安心しては足にしがみつくと大きな手が頭の上に乗った。
「おい、黙ってたら分かんねぇだろ」
ぐしゃぐしゃと乱暴に撫でられるが頭を撫でられたことがないはその行動すら憧れていたものだった。腰に腕が伸びて甚爾の太い腕の上に乗せられる。ぐずっと鼻をすすると空いている手が伸びてきて親指で涙を拭われた。
「パパとママが…」
両親の名前を言うと甚爾の眉が寄る。彼も家族という物にいい思い出などない。思い出すのは最悪な思い出ばかり…
自分たちと異質なものを排除する一族にはうんざりだ。
「…とーじと離れたくない」
友達と離れたくない一心で甚爾の胸にしがみつく。
一応仕事仲間はいるが、友達はいない甚爾はをえらく気に入っていた。今だって、に会いに毎日川へ寄っていし、近づく呪霊を切り刻んでいる。
「どういうことだ?」
「とおくへ行こうって話してた…でも行きたくない。わたし、とーじと一緒がいい」
そもそも両親と一緒に行けるかも分からないが…
「なら俺と来るか?」
は初めて誘われて驚いて小さな目を大きく見開く。
両親にもクラスメイトにもどこかへ行こうと言われたことは無かった。
「いいの?」
「俺たちは“お友達”なんだろ」
「うん!とーじのお友達!」
首を傾げた甚爾に大きく頷く。
友達とはやっぱり心強い。
「でもどうするの?」
「ガキは心配すんな」
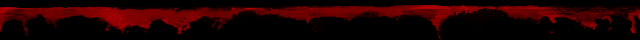
スマホ、携帯も対応しています
当サイトの夢小説は、お手元のスマートフォンや携帯電話でも読むことが可能です。
アドレスはそのまま
http://dream-novel.jp

 ピックアップする
ピックアップする