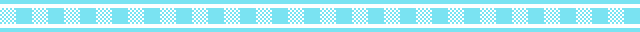
- 小
- 中
- 大
- テキストサイズ
真鍮の寂び(銀魂:銀時夢) 注:非恋愛
第1章 真鍮の寂び
強盗に襲われた翌日には引退発表、その三日後にはお登勢に万事屋の紹介を願い、襲われて一週間後の今日にはアトリエの片付けがされる。いくらなんでも迅速すぎる対応は性格故の切り替えの早さとはまた違う、何か別の執着のなさが感じられた。
そしてもう一つ不審な点がある。それは彼女が利き手を負傷していることだ。
口だけで咥えることのできるタバコと違い、煙管は手を使う。仮に煙管で一服している時に強盗が入ってきたとして、それに咄嗟で対応するのなら煙管は利き手で持つのが条件反射なのではないだろうか。条件反射に任せていれば、そもそも利き手でナイフを抑え込むことなどありえない。
では何故、煙管を持ち替えたのか。強盗犯と対峙して脅かす余裕があるのだとすれば、それこそ利き手を守りながら相手を撃退する方法だって考えつくはずである。それをあえてせず、もしわざわざ利き手を傷つけるような状況へ本人が持って行ったのだとしたら……。
完成図を知らないままパズルピースを当てはめるような推理で銀時は一つの可能性に辿り着いていた。
「絵、辞める理由が欲しかったのか?」
「ご名答」
満足そうな笑みに沿って画家の顔の皺が際立つ。
両膝をついて地面に座っていた彼女はスッと軽やかに立ち上がり、布が被さったキャンバスへとまっすぐ向かった。
「こいつを見な」
その一言とともに画家は布の一部を摘み引く。少し引っ張っただけで、あとは布が重力に従って自ら滑り落ちた。露わになったキャンバスには、まだ近代文明も天人もいない、遠いようで遠くない過去の騒々しくも楽しく生きる江戸っ子たちの姿が描かれていた。
まるで江戸の街中を歩いて、ふと肩越しに振り向いたら見えたような自然な光景。誰もが生き生きと力強く、活気に満ちている。菜の花色の着物を着た、団子屋で精を出す町娘。片手で煙管を吹かし、もう片方の手で十手を弄ぶ岡っ引き。浅黒い肌で顔に十字の傷を負っている、堅気ではないが親しみやすそうな男。その他にも様々な商人や町人が個性的に生きていた。慣れ親しんだ日本の文化が題材だから親近感が湧くのか、この作品は銀時でさえ素直に「おっ」と魅せられる。
そしてもう一つ不審な点がある。それは彼女が利き手を負傷していることだ。
口だけで咥えることのできるタバコと違い、煙管は手を使う。仮に煙管で一服している時に強盗が入ってきたとして、それに咄嗟で対応するのなら煙管は利き手で持つのが条件反射なのではないだろうか。条件反射に任せていれば、そもそも利き手でナイフを抑え込むことなどありえない。
では何故、煙管を持ち替えたのか。強盗犯と対峙して脅かす余裕があるのだとすれば、それこそ利き手を守りながら相手を撃退する方法だって考えつくはずである。それをあえてせず、もしわざわざ利き手を傷つけるような状況へ本人が持って行ったのだとしたら……。
完成図を知らないままパズルピースを当てはめるような推理で銀時は一つの可能性に辿り着いていた。
「絵、辞める理由が欲しかったのか?」
「ご名答」
満足そうな笑みに沿って画家の顔の皺が際立つ。
両膝をついて地面に座っていた彼女はスッと軽やかに立ち上がり、布が被さったキャンバスへとまっすぐ向かった。
「こいつを見な」
その一言とともに画家は布の一部を摘み引く。少し引っ張っただけで、あとは布が重力に従って自ら滑り落ちた。露わになったキャンバスには、まだ近代文明も天人もいない、遠いようで遠くない過去の騒々しくも楽しく生きる江戸っ子たちの姿が描かれていた。
まるで江戸の街中を歩いて、ふと肩越しに振り向いたら見えたような自然な光景。誰もが生き生きと力強く、活気に満ちている。菜の花色の着物を着た、団子屋で精を出す町娘。片手で煙管を吹かし、もう片方の手で十手を弄ぶ岡っ引き。浅黒い肌で顔に十字の傷を負っている、堅気ではないが親しみやすそうな男。その他にも様々な商人や町人が個性的に生きていた。慣れ親しんだ日本の文化が題材だから親近感が湧くのか、この作品は銀時でさえ素直に「おっ」と魅せられる。
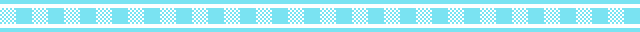
スマホ、携帯も対応しています
当サイトの夢小説は、お手元のスマートフォンや携帯電話でも読むことが可能です。
アドレスはそのまま
http://dream-novel.jp
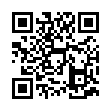
 ピックアップする
ピックアップする