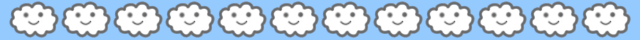
- 小
- 中
- 大
- テキストサイズ
【 ハイキュー!!】~空の色~
第37章 桜満開の心 ( 伊吹 梓 )
グラスを持った桜太がウッドデッキのベンチに座るのを見て、引き寄せられるように私もその隣に座ってみる。
桜太は、私が桜太宛てに書いた手紙を広げて便箋に目を落とす。
それが何となく恥ずかしくて、私は正面を向いたまま佇んだ。
そこから見える景色は昔見た景色と何ひとつ変わらず、あの頃と同じで。
変わってしまったのはきっと・・・私だけ。
交際中は、紡ちゃんや慧太くんとみんなで花火をしたり。
ピクニック気分をと、庭でお弁当を広げたり。
4人で・・・バレーボール遊びをしたり。
それは私が1番ヘタッピだったけど、それでもいつも笑いが溢れてた。
月日が経っても、ここには幾つもの楽しい思い出がある。
カサリと音を立てて、桜太が読み終えた手紙を丁寧に折り畳んで胸ポケットへとしまうと、暫く俯いて、それから・・・そっと空を見上げて、小さく息を吐いた。
ごめんね・・・桜太。
私、生きられなかった・・・
ごめんね・・・桜太。
私、そんなに寂しそうにしている桜太に・・・今、声もかけてあげられない・・・
ごめんね・・・
触れたくても触れられないもどかしさと、ここにいることに気付いてさえ貰えない寂しさに、ごめんねしか言えない自分に、悲しくなる。
私は、ここにいるのに。
伝わらない寂しさと、伝えられない寂しさに縛られていると、グラスの中の氷が小さな音を立てて揺れた。
桜「アホだろ慧太・・・こんなの渡してくれて」
小さなため息を逃がしながらグラスを煽った桜太が呟けば、まるでタイミングを合わせたかのように慧太君が姿を見せる。
慧「呼んだか?」
随分と久しぶりに見る慧太君は、あの頃よりもずっとワイルドな感じになっていて。
桜太と並ぶと、本当に双子の兄弟なんだろうかと思うほど見た目も雰囲気も違う。
まぁ・・・学生時代の頃も、桜太と間違える事はそもそもなかったけれど。
その事を慧太君は、自分達を間違えることがない貴重な人材だとか言って笑ってたけど。
両親でさえ、たまに間違えてるから、とか。
ごめんね、慧太君。
私が桜太と慧太君を間違えなかったのは、それは慧太君が桜太じゃないからだよ。
だから、そんな貴重な人材なんかじゃない。
桜太じゃないから、慧太君だと分かっただけ。
ただ・・・それだけ。
桜太は、私が桜太宛てに書いた手紙を広げて便箋に目を落とす。
それが何となく恥ずかしくて、私は正面を向いたまま佇んだ。
そこから見える景色は昔見た景色と何ひとつ変わらず、あの頃と同じで。
変わってしまったのはきっと・・・私だけ。
交際中は、紡ちゃんや慧太くんとみんなで花火をしたり。
ピクニック気分をと、庭でお弁当を広げたり。
4人で・・・バレーボール遊びをしたり。
それは私が1番ヘタッピだったけど、それでもいつも笑いが溢れてた。
月日が経っても、ここには幾つもの楽しい思い出がある。
カサリと音を立てて、桜太が読み終えた手紙を丁寧に折り畳んで胸ポケットへとしまうと、暫く俯いて、それから・・・そっと空を見上げて、小さく息を吐いた。
ごめんね・・・桜太。
私、生きられなかった・・・
ごめんね・・・桜太。
私、そんなに寂しそうにしている桜太に・・・今、声もかけてあげられない・・・
ごめんね・・・
触れたくても触れられないもどかしさと、ここにいることに気付いてさえ貰えない寂しさに、ごめんねしか言えない自分に、悲しくなる。
私は、ここにいるのに。
伝わらない寂しさと、伝えられない寂しさに縛られていると、グラスの中の氷が小さな音を立てて揺れた。
桜「アホだろ慧太・・・こんなの渡してくれて」
小さなため息を逃がしながらグラスを煽った桜太が呟けば、まるでタイミングを合わせたかのように慧太君が姿を見せる。
慧「呼んだか?」
随分と久しぶりに見る慧太君は、あの頃よりもずっとワイルドな感じになっていて。
桜太と並ぶと、本当に双子の兄弟なんだろうかと思うほど見た目も雰囲気も違う。
まぁ・・・学生時代の頃も、桜太と間違える事はそもそもなかったけれど。
その事を慧太君は、自分達を間違えることがない貴重な人材だとか言って笑ってたけど。
両親でさえ、たまに間違えてるから、とか。
ごめんね、慧太君。
私が桜太と慧太君を間違えなかったのは、それは慧太君が桜太じゃないからだよ。
だから、そんな貴重な人材なんかじゃない。
桜太じゃないから、慧太君だと分かっただけ。
ただ・・・それだけ。
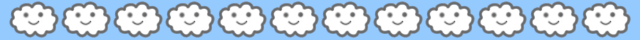
スマホ、携帯も対応しています
当サイトの夢小説は、お手元のスマートフォンや携帯電話でも読むことが可能です。
アドレスはそのまま
http://dream-novel.jp

 ピックアップする
ピックアップする