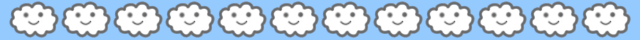
- 小
- 中
- 大
- テキストサイズ
【 ハイキュー!!】~空の色~
第26章 冬の温もり ( 牛島 若利 )
その日から、猫の様子を見に行く度に細かく書き記したメールを送るという毎日が続いた。
雨が降り出せば、濡れることのない場所へと箱を移動させ、寒くない様に使い古したタオルを入れてやる。
そういった事も、自ら進んでやるようになった。
だが。
夏も終わり、秋も深まる頃···突然猫達は姿を見せなくなった。
ロードワークから戻ると、いつもの場所にひとり佇む城戸の姿。
足元に置かれた箱をじっと見つめていてはいるようだが、その後ろ姿は寂しさで溢れていた。
「どうした」
『とうとう、巣立っちゃったみたい。朝からずっと、ここに猫達が帰って来ないの』
空っぽの箱を見つめたまま、城戸はポツリと言った。
「人の子も、いつかは親元を離れて巣立つ。ヤツらも外の世界に出て行ったんだろう」
こんな言葉しか出て来ない自分が情けなく思う。
『そう、だね。でも、急にいなくなっちゃったから···なんだか寂しいなぁ···』
涙を堪えて、瞬きをせずにいる姿を見て、思わず···
「涙を見られたくないと言うなら、隠してやる」
···抱き寄せた。
どれくらい経ったのだろう。
一向に戻らないオレを天童が探しに来るまで、小さく震える肩を包み続けた。
『ありがとう、牛島君。もう、大丈夫だから···』
泣き腫らした目を隠すように俯いたまま、城戸はオレの胸を押し返す。
「分かった、じゃあ···」
そう言い残して、オレは背中を向けて歩き出した。
天「スッゴーイ珍しいモノ見ちゃったヨ···まさか若利クンがねぇ~」
奇妙な動きをしながら、天童がオレを覗き見る。
「別に大した事じゃない。だが···なんだ、この感情は」
天「ん~?」
「天童。お前がオレを呼びに来た時から、何とも例え難い感情が沸き立っている」
天「若利クン?それって···マジで言ってる?」
そうだと答えれば、天童は驚きの顔を全面に出して固まっていた。
天「無自覚って、コワイ」
「どういうことだ」
天「教えナーイ!」
「なぜだ」
天「んン~!···オモシロイから!」
訊ねる相手が悪かったと言うことか。
「まぁ、いい。いつか分かることだ」
ゆっくり時間をかけて考えれば、解けない問題などない。
その時はそれでいいと、そう、思っていたのに。
雨が降り出せば、濡れることのない場所へと箱を移動させ、寒くない様に使い古したタオルを入れてやる。
そういった事も、自ら進んでやるようになった。
だが。
夏も終わり、秋も深まる頃···突然猫達は姿を見せなくなった。
ロードワークから戻ると、いつもの場所にひとり佇む城戸の姿。
足元に置かれた箱をじっと見つめていてはいるようだが、その後ろ姿は寂しさで溢れていた。
「どうした」
『とうとう、巣立っちゃったみたい。朝からずっと、ここに猫達が帰って来ないの』
空っぽの箱を見つめたまま、城戸はポツリと言った。
「人の子も、いつかは親元を離れて巣立つ。ヤツらも外の世界に出て行ったんだろう」
こんな言葉しか出て来ない自分が情けなく思う。
『そう、だね。でも、急にいなくなっちゃったから···なんだか寂しいなぁ···』
涙を堪えて、瞬きをせずにいる姿を見て、思わず···
「涙を見られたくないと言うなら、隠してやる」
···抱き寄せた。
どれくらい経ったのだろう。
一向に戻らないオレを天童が探しに来るまで、小さく震える肩を包み続けた。
『ありがとう、牛島君。もう、大丈夫だから···』
泣き腫らした目を隠すように俯いたまま、城戸はオレの胸を押し返す。
「分かった、じゃあ···」
そう言い残して、オレは背中を向けて歩き出した。
天「スッゴーイ珍しいモノ見ちゃったヨ···まさか若利クンがねぇ~」
奇妙な動きをしながら、天童がオレを覗き見る。
「別に大した事じゃない。だが···なんだ、この感情は」
天「ん~?」
「天童。お前がオレを呼びに来た時から、何とも例え難い感情が沸き立っている」
天「若利クン?それって···マジで言ってる?」
そうだと答えれば、天童は驚きの顔を全面に出して固まっていた。
天「無自覚って、コワイ」
「どういうことだ」
天「教えナーイ!」
「なぜだ」
天「んン~!···オモシロイから!」
訊ねる相手が悪かったと言うことか。
「まぁ、いい。いつか分かることだ」
ゆっくり時間をかけて考えれば、解けない問題などない。
その時はそれでいいと、そう、思っていたのに。
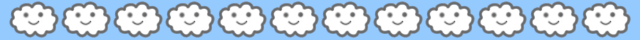
スマホ、携帯も対応しています
当サイトの夢小説は、お手元のスマートフォンや携帯電話でも読むことが可能です。
アドレスはそのまま
http://dream-novel.jp

 ピックアップする
ピックアップする