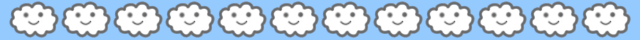
- 小
- 中
- 大
- テキストサイズ
【 ハイキュー!!】~空の色~
第26章 冬の温もり ( 牛島 若利 )
名前を聞けば、同じ学年の城戸紡と知った。
名前だけは、天童からの話で知っていた。
ちょっと変わり者の、秀才だと。
天童から変わり者と聞いて、余程変わっているのだろうと思っていたが。
目の前の人物は、ごく普通の女生徒で。
まぁ、白衣なんて着てる辺りが変わっていると言えば変わっているのだろう。
それからはロードワークが終わる度に体育館の裏を覗き、小さな後ろ姿と猫の姿を見つけると、声を掛けるようになった。
そして季節が流れて行き、春の終わりに近付く頃···
『あ、牛島君!今日はビックリなニュースがあるんだよ!』
オレの姿を見つけ手招く姿に、思わず眉をひそめた。
「なんのニュースだ」
『あのね!この子がお母さんになったの!凄いよね!』
見て!と箱の中を指差しながら、オレの手を掴み屈ませる。
箱の中には横たわる見慣れた猫の姿と、それから、小さくもモゾモゾと動く2匹の子猫。
まだ目も開いていない、新しい命がそこにあった。
『凄いよねぇ、もうお母さんになっちゃったんだね』
嬉しそうに猫の頭を撫でては、同じ事を何度も繰り返し言う彼女に···なぜか胸が暖かくなった。
「触っても大丈夫なのか?」
『この子は大丈夫だけど、赤ちゃんは絶対触っちゃダメ』
「産まれたばかりだからか?」
『違うよ。出産したばかりの猫は、赤ちゃんに人間の匂いがつくと···育てなくなっちゃうから。酷い時は、食べちゃったりもするみたい』
その原理はよく分からないけど、子供の頃にそういう経験をしたからだと悲しげな顔を見せていた。
『あのさ、牛島君?お願いがあるんだけど···』
「なんだ」
『牛島君って、寮生だよね?』
「そうだが、それがどうかしたか?」
『私がいない時、この子たちにご飯とかあげてもらえないかな?』
···オレが?
なぜだ、と問えば。
白鳥沢には珍しく、寮生ではないから部活やサークル活動が終われば学校内に入る事が出来ないからだと返された。
オレが···世話を?
出来るのか?
いや、やるしかないだろう。
小さな命を見捨てる訳には行かない。
「分かった、引き受けよう。その代わり···」
何かあった時に困るからという理由を付けて、連絡先を交換した。
決して、興味本位でそうした訳じゃない。
何かあった時の為、だけだ。
名前だけは、天童からの話で知っていた。
ちょっと変わり者の、秀才だと。
天童から変わり者と聞いて、余程変わっているのだろうと思っていたが。
目の前の人物は、ごく普通の女生徒で。
まぁ、白衣なんて着てる辺りが変わっていると言えば変わっているのだろう。
それからはロードワークが終わる度に体育館の裏を覗き、小さな後ろ姿と猫の姿を見つけると、声を掛けるようになった。
そして季節が流れて行き、春の終わりに近付く頃···
『あ、牛島君!今日はビックリなニュースがあるんだよ!』
オレの姿を見つけ手招く姿に、思わず眉をひそめた。
「なんのニュースだ」
『あのね!この子がお母さんになったの!凄いよね!』
見て!と箱の中を指差しながら、オレの手を掴み屈ませる。
箱の中には横たわる見慣れた猫の姿と、それから、小さくもモゾモゾと動く2匹の子猫。
まだ目も開いていない、新しい命がそこにあった。
『凄いよねぇ、もうお母さんになっちゃったんだね』
嬉しそうに猫の頭を撫でては、同じ事を何度も繰り返し言う彼女に···なぜか胸が暖かくなった。
「触っても大丈夫なのか?」
『この子は大丈夫だけど、赤ちゃんは絶対触っちゃダメ』
「産まれたばかりだからか?」
『違うよ。出産したばかりの猫は、赤ちゃんに人間の匂いがつくと···育てなくなっちゃうから。酷い時は、食べちゃったりもするみたい』
その原理はよく分からないけど、子供の頃にそういう経験をしたからだと悲しげな顔を見せていた。
『あのさ、牛島君?お願いがあるんだけど···』
「なんだ」
『牛島君って、寮生だよね?』
「そうだが、それがどうかしたか?」
『私がいない時、この子たちにご飯とかあげてもらえないかな?』
···オレが?
なぜだ、と問えば。
白鳥沢には珍しく、寮生ではないから部活やサークル活動が終われば学校内に入る事が出来ないからだと返された。
オレが···世話を?
出来るのか?
いや、やるしかないだろう。
小さな命を見捨てる訳には行かない。
「分かった、引き受けよう。その代わり···」
何かあった時に困るからという理由を付けて、連絡先を交換した。
決して、興味本位でそうした訳じゃない。
何かあった時の為、だけだ。
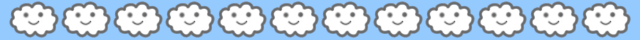
スマホ、携帯も対応しています
当サイトの夢小説は、お手元のスマートフォンや携帯電話でも読むことが可能です。
アドレスはそのまま
http://dream-novel.jp

 ピックアップする
ピックアップする