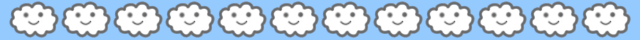
- 小
- 中
- 大
- テキストサイズ
【 ハイキュー!!】~空の色~
第26章 冬の温もり ( 牛島 若利 )
また、か。
もうここにはいないと分かっているのに、つい···その場所に目が行ってしまう。
もう、1年経つんだな。
紡···
天「わっかと~しク~ン?隣座ってイイ?」
「良いも何も、既に座っているだろう」
天「バレたァ?」
妙に機嫌のいい天童が、食事プレートをテーブルに置いてオレをジッと見る。
「何だ」
天「若利クンさぁ、また見てたでしょ?···あそこの席」
「それがどうかしたか?」
素っ気なく答えれば、天童はニタリと笑って見せた。
天「かわいかったよね?つーちゃんってさ。今頃は海の向こうでモッテモテ~!な毎日を過ごしてるかもヨ?」
「天童、静かに食べろ」
触れたれたくない傷跡に塩を塗り込むような発言に、思わず更に素っ気なくなる。
天「やっぱり、まだ···忘れられない?」
そう言ってくる天童の言葉を流し、紡と出会った頃の事を密かに思い出した。
ニャ~ン···
『こら、邪魔しちゃダメなの』
部活の前のロードワークから戻ると、体育館の裏の方から猫の鳴き声と、それから人の声が聞こえてきた。
こんなところで、誰だ?
そう思ったオレは、引き寄せられるかのように足を向けた。
ニャ~ン···
『もうちょっと待っててね?そしたら遊んであげるから、分かった?』
猫の頭を撫でながら言って、手にしたバインダーに何かを書き込む後ろ姿。
白衣を着ているという事は、研究サークルか何かの部員か?
時折、目の前にある花壇に目を向けては、また、何かを書き込んでいる。
何を、しているのだろう。
無意識にもう一歩だけ、前に進む。
ジャリ···と音が立ち、それに驚いた猫が走り去って行った。
『あっ···行っちゃったか···今日はおやつ、まだあげてなかったんたけどな』
小さく息をつき、白衣のポケットからお菓子のようなものを取り出して眺めては、またポケットに戻した。
「···スマン。どうやらオレが猫を驚かせてしまったようだ」
振り返ることのない小さな背中に声をかけると、軽く肩を跳ねながらオレを見た。
『あ···牛島君?』
「なぜ、オレの名を?」
『なぜ?って、この学校の生徒なら知らない人はいないんじゃないかな?だって牛島君、有名人だから』
有名?と返せば、バレー部のエースなんでしょ?と笑っている。
もうここにはいないと分かっているのに、つい···その場所に目が行ってしまう。
もう、1年経つんだな。
紡···
天「わっかと~しク~ン?隣座ってイイ?」
「良いも何も、既に座っているだろう」
天「バレたァ?」
妙に機嫌のいい天童が、食事プレートをテーブルに置いてオレをジッと見る。
「何だ」
天「若利クンさぁ、また見てたでしょ?···あそこの席」
「それがどうかしたか?」
素っ気なく答えれば、天童はニタリと笑って見せた。
天「かわいかったよね?つーちゃんってさ。今頃は海の向こうでモッテモテ~!な毎日を過ごしてるかもヨ?」
「天童、静かに食べろ」
触れたれたくない傷跡に塩を塗り込むような発言に、思わず更に素っ気なくなる。
天「やっぱり、まだ···忘れられない?」
そう言ってくる天童の言葉を流し、紡と出会った頃の事を密かに思い出した。
ニャ~ン···
『こら、邪魔しちゃダメなの』
部活の前のロードワークから戻ると、体育館の裏の方から猫の鳴き声と、それから人の声が聞こえてきた。
こんなところで、誰だ?
そう思ったオレは、引き寄せられるかのように足を向けた。
ニャ~ン···
『もうちょっと待っててね?そしたら遊んであげるから、分かった?』
猫の頭を撫でながら言って、手にしたバインダーに何かを書き込む後ろ姿。
白衣を着ているという事は、研究サークルか何かの部員か?
時折、目の前にある花壇に目を向けては、また、何かを書き込んでいる。
何を、しているのだろう。
無意識にもう一歩だけ、前に進む。
ジャリ···と音が立ち、それに驚いた猫が走り去って行った。
『あっ···行っちゃったか···今日はおやつ、まだあげてなかったんたけどな』
小さく息をつき、白衣のポケットからお菓子のようなものを取り出して眺めては、またポケットに戻した。
「···スマン。どうやらオレが猫を驚かせてしまったようだ」
振り返ることのない小さな背中に声をかけると、軽く肩を跳ねながらオレを見た。
『あ···牛島君?』
「なぜ、オレの名を?」
『なぜ?って、この学校の生徒なら知らない人はいないんじゃないかな?だって牛島君、有名人だから』
有名?と返せば、バレー部のエースなんでしょ?と笑っている。
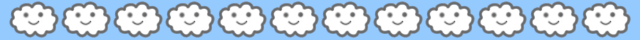
スマホ、携帯も対応しています
当サイトの夢小説は、お手元のスマートフォンや携帯電話でも読むことが可能です。
アドレスはそのまま
http://dream-novel.jp

 ピックアップする
ピックアップする