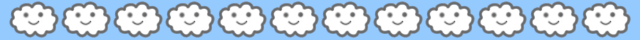
- 小
- 中
- 大
- テキストサイズ
夢に見た世界【アイドリッシュセブン】【D.Gray-man】
第1章 恋人同士とは(i7)完
こんな結果、誰が想像できただろう。
近くにあったホテル、ではなくここはファミリーレストラン。
確かに、私はおなかがすいたと言った。
言ったけれど、空腹という意味で言ったんじゃない!
目の前の男性は、感情の読めないニコニコとした表情で、私と同じテーブル席の向かい側に座っている。
「私、もっと刹那的な意味でおじさんに言ったんですけど」
「キミみたいな若い子が、そういう事を軽々しく口にするもんじゃないよ。大人をからかって遊んでるつもりなら、もっと他に面白い事を見つけるんだ。例えば、アイドルとかね」
大人をからかうな、か。
からかってるつもりは無いんだけどな。
男の人は若い女の子が好きだし、私は気晴らしがしたい。
ウィンウィンの関係だと思うんだけど。
私、処女でもないし。
そういう事するの嫌いじゃないし。
年上にしか興味無いんだから、良いじゃん?
って思う。
でも、このおじさんは違うんだな。
世の中には色んな人が居る。
私を拾って一晩の思い出をくれる人が、一般的な人に分類されるのかどうかも分からない。
私はそういうの普通だと思ってるけど、他の人にとっては普通じゃない。
このおじさんみたいに。
それにしても、よりによってアイドルとは。
「私、アイドルは興味無いの。みんなが好きな物を私も好きなんて、誰が決めたの?」
私が答えると、おじさんは少し考えるように間を開けて、それから肘をついて両手を組む。
これは長い説教されるかなと思ったら、おじさんは。
「確かに、キミの言う通りだ。ごめんね、おじさんも偏見を持ってキミを見てしまっていたね。じゃあ教えてくれるかな、キミ名前は? どうして、あんな事を言ったんだい?」
と、すごく対等に話そうとしてくれた。
私は、そんな大人に出会った事が無かったからすごく驚いてしまって。
「名前、は、香住カエデ、です」
気がついたら自分から、色々と話し始めてしまっていた。
見ず知らずのおじさんに、名前も知らないおじさんに、自分の事を洗いざらい、話している。
それは、どこかこそばゆくて、でも嫌な気持ちはしなかった。
おじさんは、私のつまらない話を最後まで聞いてくれて、時々相槌を打つ以外には何も言わないでいてくれた。
近くにあったホテル、ではなくここはファミリーレストラン。
確かに、私はおなかがすいたと言った。
言ったけれど、空腹という意味で言ったんじゃない!
目の前の男性は、感情の読めないニコニコとした表情で、私と同じテーブル席の向かい側に座っている。
「私、もっと刹那的な意味でおじさんに言ったんですけど」
「キミみたいな若い子が、そういう事を軽々しく口にするもんじゃないよ。大人をからかって遊んでるつもりなら、もっと他に面白い事を見つけるんだ。例えば、アイドルとかね」
大人をからかうな、か。
からかってるつもりは無いんだけどな。
男の人は若い女の子が好きだし、私は気晴らしがしたい。
ウィンウィンの関係だと思うんだけど。
私、処女でもないし。
そういう事するの嫌いじゃないし。
年上にしか興味無いんだから、良いじゃん?
って思う。
でも、このおじさんは違うんだな。
世の中には色んな人が居る。
私を拾って一晩の思い出をくれる人が、一般的な人に分類されるのかどうかも分からない。
私はそういうの普通だと思ってるけど、他の人にとっては普通じゃない。
このおじさんみたいに。
それにしても、よりによってアイドルとは。
「私、アイドルは興味無いの。みんなが好きな物を私も好きなんて、誰が決めたの?」
私が答えると、おじさんは少し考えるように間を開けて、それから肘をついて両手を組む。
これは長い説教されるかなと思ったら、おじさんは。
「確かに、キミの言う通りだ。ごめんね、おじさんも偏見を持ってキミを見てしまっていたね。じゃあ教えてくれるかな、キミ名前は? どうして、あんな事を言ったんだい?」
と、すごく対等に話そうとしてくれた。
私は、そんな大人に出会った事が無かったからすごく驚いてしまって。
「名前、は、香住カエデ、です」
気がついたら自分から、色々と話し始めてしまっていた。
見ず知らずのおじさんに、名前も知らないおじさんに、自分の事を洗いざらい、話している。
それは、どこかこそばゆくて、でも嫌な気持ちはしなかった。
おじさんは、私のつまらない話を最後まで聞いてくれて、時々相槌を打つ以外には何も言わないでいてくれた。
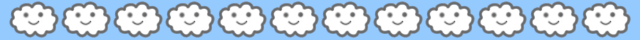
スマホ、携帯も対応しています
当サイトの夢小説は、お手元のスマートフォンや携帯電話でも読むことが可能です。
アドレスはそのまま
http://dream-novel.jp

 ピックアップする
ピックアップする