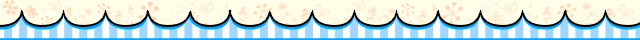
- 小
- 中
- 大
- テキストサイズ
俺のコタンは、あなたの腕
第2章 一番の
「やぁ。」
「やぁ。じゃない。」
しばらくは小樽に居る。と電報を律儀に送っておいてやった。
やさしいだろう?
「良いか十兵衛。こうして人を呼びつけて金取って。お前を生活させてるのは俺の財布か?あ?」
「うぅん。ひゃくのすけぇ。」
「へっ。はいはい。」
この百之助。
尾形百之助と言う男は、昔馴染みの知り合いだ。
陸軍の軍人で、軍から客を引っ張ってきてくれる窓口。
ひと組の褥の敷かれた暗い部屋で、百之助にしな垂れかかれば、あっという間に熱っぽい吐息が漏れる。
「なんだ。今日はやけに積極的だな。」
「百之助とは久しぶりだから。」
「寂しかった?」
「ばか。」
「ばか?おい。陸軍様に向かって馬鹿とは。」
ムカつく。
いや、図星だったのが恥ずかしくて百之助の坊主頭を、じゃりじゃりじゃりじゃりじゃり。
「よせ。」
「ふふふ。」
「よせって!」
「うあっ。アッ。」
「俺もだったんだよ!黙って抱かれてろ。」
「ばっか!」
がぶがぶがぶがぶ。
ぎゅうううううううううう。と色んなところを締めつける。
どこかって?
そんなの考えろよ、自分で。
夜が明ける前にケロリとして百之助は出て行く。
「何しに行くんだ?」
「うーん。これからもお前を食わす為にな。」
「仕事はあっちだろ?違う。山になにしに行くんだ?って聞いてんの。」
「うーん?」
百之助は気障に笑って俺の唇を食む。
食むっつうか、噛む。
血が出た。
「あの。いてぇんすけど。」
「俺だろ?飯食う度に俺を思い出せる。いいだろ?」
「他の客が真似する。」
「なんだよ。俺はお前の客か。客どまりか。」
「他の客と何が違う?」
冬の朝。
それも本当に早い朝。
息が白いのは当然で、鼻で思い切り息を吸えば鼻毛が凍る。
肺が冷えると体が冷える。
だからあまり口を開けず、体を開かず、小さな口で短く喋る。
「なんだよ。あれだけ愛して分からねぇか。」
「愛?俺の体に噛みつくのが愛だと?」
「愛情表現さ。」
「獣か。いいや。行けよ。」
「移動するならまた連絡寄こせ。」
「はいはい。じゃぁ。」
あっさりしているもんだと思う。
ありゃ山猫だ。
こっちゃぁ家猫。
猫どうし気が合う。
次に百之助に会えるのはいつになるだろうか。
(ク・セマシテク)
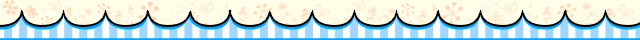
スマホ、携帯も対応しています
当サイトの夢小説は、お手元のスマートフォンや携帯電話でも読むことが可能です。
アドレスはそのまま
http://dream-novel.jp

 ピックアップする
ピックアップする