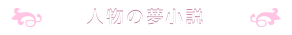夢小説 -ドリームノベル-
みんなの大好きな夢小説が読める・書ける
女の子は誰だってヒロイン……。
いつだって恋して夢を見ていたい……。
あなたの夢、ドリームノベルで叶えてみませんか?
小説内に登場する主要キャラクターの名前を
自分の好きな名前へ変換する機能がついた小説です。
他にもドリーム小説やドリー夢小説などと呼ばれています。
ドリームノベルは、この機能[名前変換]="ドリーム設定"に特化した小説投稿サイトです。"ドリーム設定"を使うことにより、小説を読む際に登場キャラクターへより深い感情移入をすることが可能になるのです!!
自分の好きな名前へ変換する機能がついた小説です。
他にもドリーム小説やドリー夢小説などと呼ばれています。
ドリームノベルは、この機能[名前変換]="ドリーム設定"に特化した小説投稿サイトです。"ドリーム設定"を使うことにより、小説を読む際に登場キャラクターへより深い感情移入をすることが可能になるのです!!